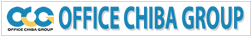自然のいとなみは、悠久の時間の積み重ねの証明です。 自然のいとなみは、悠久の時間の積み重ねの証明です。一度と同じ現象のない「天気」も、また自然のいとなみのひとつです。 悠久のいとなみの中から、先人達が、そして今も時間と英知をかけて、天気に対するいくつかの規則を見いだそうとしています。 そんな「天気」についてお話をします。 |
by Nobuyuki Chiba |
||
|
||
 最近の天気予報は、気象衛星(ひまわり)やアメダス、気象レーダーなどから把握し、私たちはテレビ等でかなり高い確率で情報を得ることが出来ます。それでも専門化が予測しても確立は100パーセントではないと言われます。 なおさら知識がない私たちにとっては、天気について予測することは難しく大変です。また天気を予測するには、天気図を書くことができそして天気図を見る知識が必要です。その前提として気圧、風 前線、等圧線等いろいろ学ばなければなりません。そこで、ここでは何故という理屈を省き、基本的な事柄を簡単に述べます。 日本は海に囲まれ季節の変化に富んでおります。天気は地域、地形、そして季節風等によっても異なります。 ではまた次回へ。 |
||
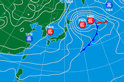 新聞等の天気図をみて日本列島が高気圧におおわれている時天気は良く、また高気圧が張り出してくると予想される時天気が良くなります。反対に低気圧が発生している時は天気は良くありませんし、低気圧が接近すると天気はだんだ悪くなります。例えば、低気圧が発生していても西の方から高気圧が張り出してきますと、天気は西から東へ推移しますので天気は回復します。 ではまた次回へ。 |
||
 次に低気圧と等圧線の関係です。天気図を見て低気圧が発生しており、その等圧線の間隔が狭いときは風が強く吹きますが、等圧線の間隔が広いときは風が弱く吹きます。 ではまた次回へ。 |
||
 風は冷たい空気や湿った空気を運んできて天気を変化させます。例えば晴れて暖かい空気のところへ、冷たい空気が流れ込んでくると、気温は下がり天気が変わります。そのため冬には北または北西の冷たい風が吹き、日本海側に雪を降らせます。 ではまた次回へ。 |
||
 天気予報でよく次の言葉を耳にします。気圧の谷とか前線です。気圧の谷とは二つの高気圧にはさまれた気圧の低いところです。気圧の谷から低気圧と前線が発生します。 ではまた次回へ。 |
||
| |
||
 梅雨とは北海道を除く日本一帯に、毎年六月から七月にかけて続く曇りや長雨のことです。春から夏への変わり目とも言えます。私たちは梅雨に入ることを入梅などと表現します。 ではまた次回へ。 |
||
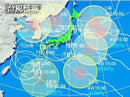 最大風速17メートル以上のものを台風と呼びます。強い風や強いにわか雨を伴い大きな被害をもたらすこともあります。台風発生の原因ははっきり解明されていませんが、赤道より少し北の熱帯収束帯の地域、具体的にフィリピンの横側南シナ海で発生します。 ではまた次回へ。 |
||
 梅雨が明け、太平洋高気圧が日本全体をおおうようになりますと夏がやってきます。小笠原諸島付近を中心に高温で多湿の空気のかたまり気団が、南の海上から日本列島をおおうので日本では小笠原高気圧とも呼ばれます。蒸し暑い夏の気候をもたらします。 ではまた次回へ。 |
||
| |
||
 湿度とは大気中に含まれる水蒸気の量すなわち空気中の水分の割合を言います。気温が高いと空気中におおくの水分が集まり湿度が高くなります。反対に気温が低いと空気が乾燥し湿度が低くなります。夏は気温が高いので湿度が高くより暑く感じ、冬は気温が低いので湿度が低く寒く感じます。梅雨の時期に蒸し暑く感じるのは、空気中の水分が多く湿度が高いからです。 ではまた次回へ。 |
||
| |
||
 天気予報で冬型の気圧配置という言葉を耳にします。これは日本列島の西側に高気圧があり、東側の太平洋上に低気圧がある状態のことで、西高東低の気圧配置であることを意味します。また等圧線が南北に並ぶのが冬型の気圧配置の特徴です。冷たい北西の季節風が吹き等圧線の間隔が狭いと風も強く吹きます。 ではまた次回へ。 |
||
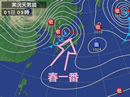 春一番とは冬から春に移り変わる時季に、初めて吹く強い南風を言います。例年二月から三月半ばの間に吹きます。春一番により日本海で低気圧が発達し南寄りの強風が吹くので気温が上昇します。 ではまた次回へ。 |
||
 開花予想日は数回行なわれ初めは三月上旬頃に発表されます。桜は芽が夏に作られそして秋・冬の低温を経て春の気温の上昇とともに成長し開花します。よって暖かい地方から開花していきます。 また開花具合によって咲き始め、三分咲き、五分咲き、七分咲き、満開、散り始めなどと表現されます。 ではまた次回へ。 |
||